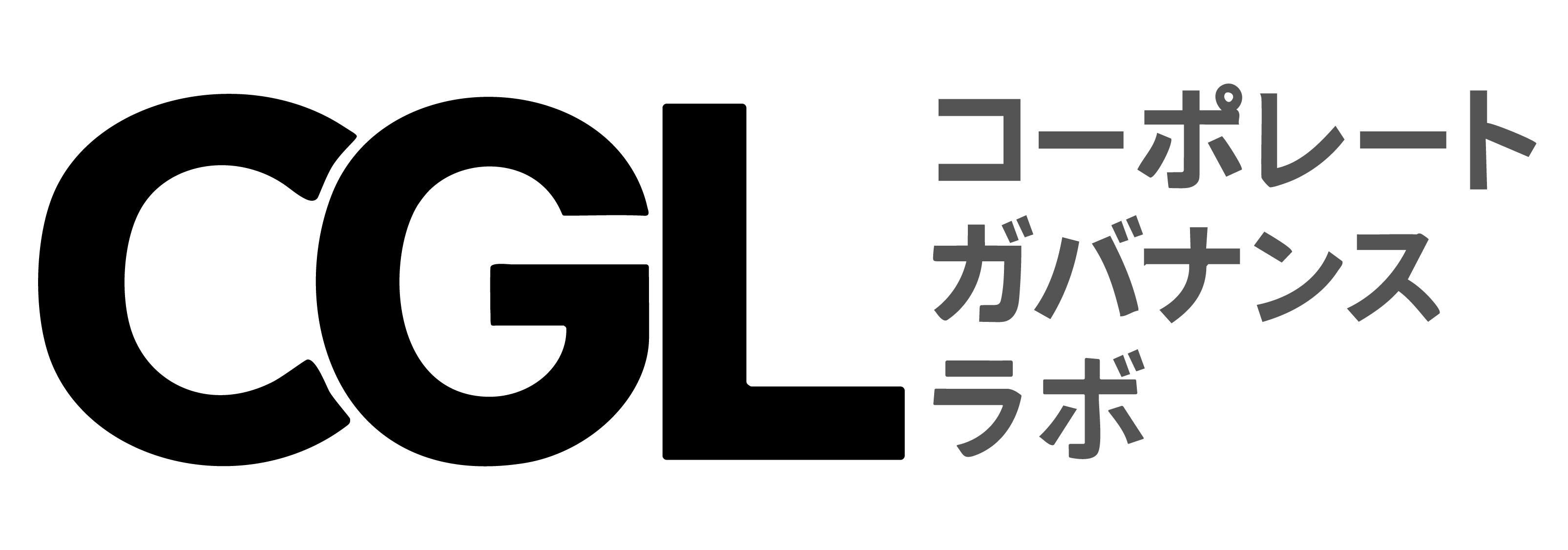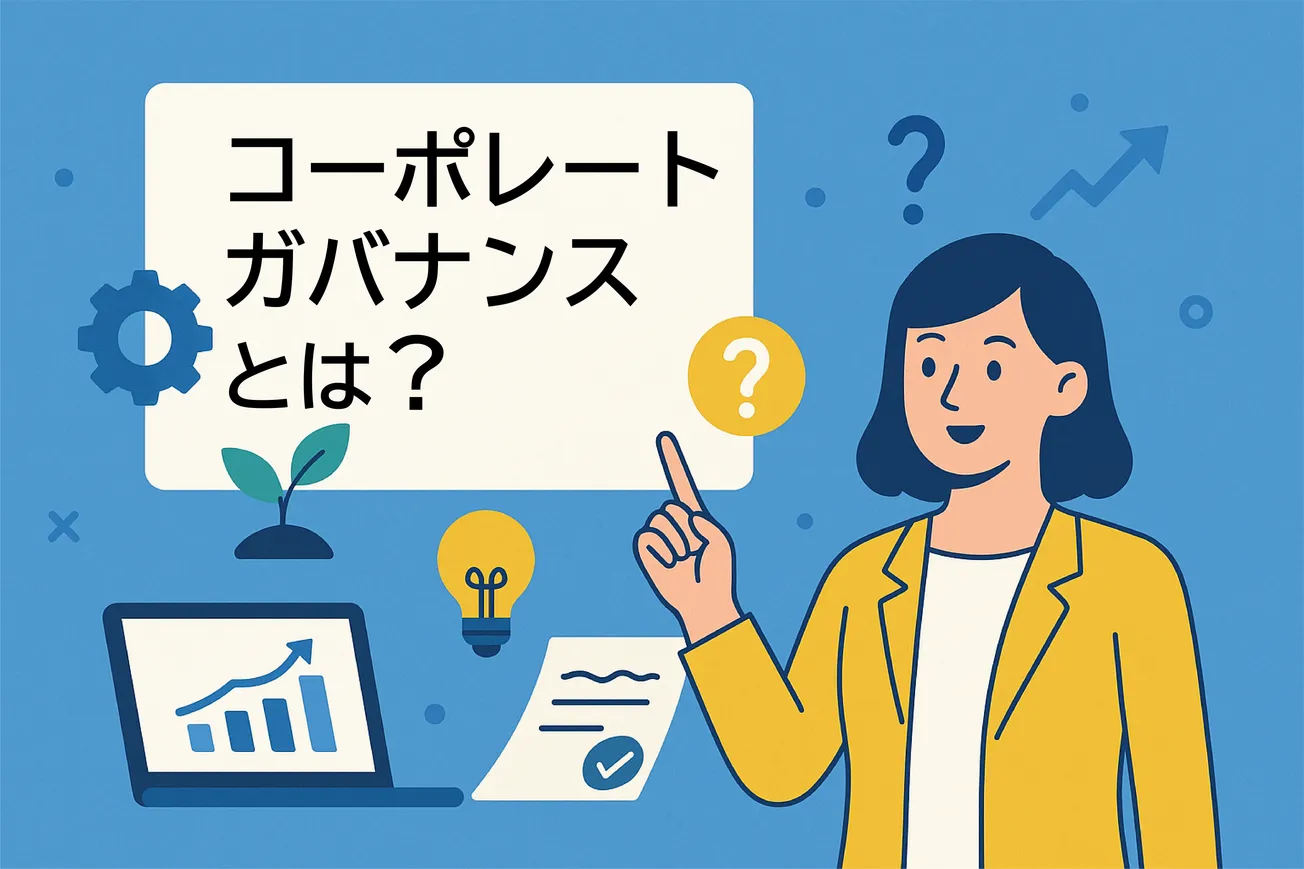目次
2025年、金融庁の有識者会議において日本版スチュワードシップ・コード(機関投資家の諸原則)の改訂案が議論されました。3月には改訂案(第4版)が公表され、実質株主の透明性向上や協働エンゲージメントの促進など企業と投資家の対話を「実質化」する論点が示されています。上場企業にとっても、このコード改訂は情報開示の在り方に大きな影響を及ぼします。そこで本記事では、スチュワードシップ・コード改訂で変わる上場企業の開示5つの要点を整理し、最新の議論内容を踏まえた実務的視座を提供します。
株主情報の開示とエンゲージメント強化
まず注目すべきは、株主(機関投資家)側の情報開示姿勢が変わる点です。現行制度では5%超の大口保有者以外の実質株主を企業が把握することは容易ではなく、調査会社の活用や投資家との個別面談によりコストをかけ株主情報を収集せざるを得ませんでした。今回のコード改訂案では、この課題に対応し「機関投資家は投資先企業から求められた場合、自らの保有株式数を企業に説明すべき」との指針(新指針4-2)が盛り込まれました。これは企業と投資家の建設的な対話を促進するため、対話の前提として株主構成の透明性を高める狙いがあります。
上場企業にとって、この変化は株主情報の「見える化」を進める好機です。主要株主を正確に把握し、その関心やスタンスを踏まえて株主ごとに戦略的なエンゲージメントを図ることが可能となります。また、機関投資家側から保有状況の開示を得られるようになることで、企業側からも対話の場を設けやすくなります。例えば:
- 主要株主への定期的な説明会開催: 上位株主に対し経営トップ自ら事業戦略や中長期計画を説明し、フィードバックを得る場を設ける。
- 株主構成のモニタリング強化: 四半期ごとに株主名簿を分析し、新規に浮上した機関投資家や持株比率の変化を把握する。必要に応じてIR担当からアプローチする。
こうした取り組みにより、企業と株主の信頼関係構築が進み、中長期的な建設的対話の土台が強化されるでしょう。
協働エンゲージメントやアクティビスト対応の“見える化”
二つ目の要点は、複数の機関投資家による協働エンゲージメント(共同で企業と対話する取り組み)の重要性と、アクティビスト対応の透明化です。改訂案では、機関投資家に対し「必要に応じて他の機関投資家と協働して対話を行うことも選択肢として検討すべき」と明記されました。協働で企業と向き合う意義が明確に強調された形です。
この背景には、日本企業に対するアクティビスト(物言う株主)の働きかけが年々活発化している現状があります。2023年には株主提案が過去最多となり、2024年もアクティビストの攻勢は続く見通しです。近年は従来ターゲットになりやすかった中小型株だけでなく、大企業に対しても思い切った提案が行われるようになってきました。複数の株主が結束して経営改革を促す場面が増えれば、企業側もその動きを無視できません。
上場企業としては、協働エンゲージメントやアクティビストへの対応状況を「見える化」することが求められます。具体的には、以下のような情報開示や対策が考えられます:
- 株主提案や要望への対応方針を開示: アクティビストから提案があった場合、その内容と会社の対応(受け入れた施策や否決した理由等)をリリースや株主総会招集通知で説明する。他の機関投資家にも会社のスタンスを明示し、理解を得る。
- エンゲージメント活動の報告: 統合報告書やサステナビリティ報告において、「主要株主との対話状況」として年間何件の対話を行い、どのような意見交換をしたか概括する。
協働エンゲージメントの進展により、経営陣にとっては複数の株主が共通の懸念を持っているシグナルを早期に捉えることができます。また、こうした対話のプロセスを透明化することで、他の投資家やステークホルダーにも「当社は株主の声に真摯に耳を傾け、建設的な提案には協働的に取り組む」という前向きな姿勢を示せます。結果として株主との信頼関係が深まり、敵対的な状況を未然に防ぐ効果も期待できます。
中長期的企業価値を示すKPIのタイムリー開示(財務・非財務)
三つ目の要点は、中長期的な企業価値を測る指標(KPI)のタイムリーな開示です。ステークホルダーとの対話を「実質」あるものにするには、短期的な業績数値だけでなく、企業の将来価値や持続的成長性を示すデータの共有が不可欠です。投資家側もエンゲージメントを通じて企業の中長期ビジョンや戦略の進捗を把握したいと考えており、財務・非財務を問わず重要KPIをタイムリーに開示することが求められます。
企業はROE(自己資本利益率)やROICなどの資本効率指標、EBITDA成長率といった長期収益力の指標から、温室効果ガス排出量や従業員エンゲージメントといったESG指標まで、財務・非財務双方の重要KPIを設定し、それらを定期的かつ迅速に開示することが求められます。
なお2025年3月には日本で初めてサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)が策定され、国際基準(ISSB)を取り入れた非財務情報開示の枠組みが整いました。今後、財務情報と同様に信頼性の高い非財務KPIの開示が求められていくでしょう。
このようなKPIを積極的に情報開示することは「攻め」のIR戦略とも言えます。指標を通じて経営の自信と透明性を示せば、投資家との対話に具体性が生まれ、中長期的な企業価値評価につながるでしょう。例えば「ESG目標の◯%達成」や「顧客満足度◯点」といった数字を示すことで、株主にも経営の長期ビジョンが伝わりやすくなります。
フェア・ディスクロージャー・ルールと英文開示の徹底
四つ目の要点は、フェア・ディスクロージャー・ルール(FDルール)の遵守徹底と英文開示の充実です。機関投資家との個別対話が活発化する中で、未公表の重要情報を特定の株主だけに伝えてしまうリスクにも注意が必要です。今回のスチュワードシップ・コード改訂では、この点について「企業との対話において未公表の重要事実を受領することは基本的に慎重に考えるべき」との一文がガイドラインに追加され、脚注でFDルールへの言及が盛り込まれました。これは投資家側への注意喚起ですが、裏を返せば企業側も選別的な情報開示を避け、公平な開示に徹することが改めて求められていると言えます。
具体的には、IRミーティングや決算説明会でのQ&Aなどにおいて、未公開の業績見通しや重要な計画について言及しないガイドラインを社内で周知徹底する必要があります。企業側・投資家側の双方がFDルールを十分理解して対話に臨むことが重要です。もし対話の中で株主からインサイダー情報に該当し得る質問が出た場合には、「現時点でお答えできる情報は開示済のものに限られる」旨を明確に伝えるなど、公平性の確保を最優先に対応すべきです。
加えて、グローバルな投資家と対等な対話を行うためには英文での情報開示が不可欠です。東京証券取引所はプライム市場において、2025年4月以降は決算短信や適時開示情報の英語版を日本語と同時に開示することを義務化します。実際、大半のプライム企業が既に英文開示に取り組んでいますが、日本語発表から英語版公開までタイムラグがある企業も多く、更なる改善が求められています。英文開示の徹底にあたっては以下のポイントが重要です:
- 開示タイミングの同期: 決算資料やプレスリリースは、日本語版と英語版を同時に公開できる体制を整える(翻訳プロセスの前倒しや専門スタッフの配置)。
- 英文情報の範囲拡大と利便性向上: 決算短信や有価証券報告書だけでなく、IR説明会資料や株主総会招集通知、コーポレートガバナンス報告書なども可能な限り英訳して提供する。英語版IRサイトも整備し、日本語サイトと同等の情報量・更新頻度で運用する。重要情報が英語で容易に入手できる環境を作る。
英文開示を徹底することは、海外投資家との「情報格差」を解消し、公平な投資判断の機会を保証する意味があります。それにより企業はグローバルな投資マネーを呼び込みやすくなり、自社株評価の適正化にもつながります。
経営主導で進める内部体制と開示プロセス改革
最後の五つ目の要点は、経営トップ主導での内部体制整備と開示プロセスの改革です。情報開示の質とスピードを高めるには、単にIR部門任せにするのではなく、経営陣がコミットして組織横断的な体制を構築する必要があります。経営陣(CEOやCFO)がこれら会議に参画し、開示方針やメッセージ統一の指揮を執ることで、情報開示が企業戦略と一体化していきます。また、開示プロセス改革の一環としてデジタル技術の活用も有効です。例えば:
- 開示業務のDXと情報一元管理: 決算データの集計・資料作成にRPAを導入して効率化し、開示までのリードタイムを短縮する。また、財務情報やESGデータを一元管理するデータベースを構築し、必要な情報を迅速に取り出せるようにする。
- 社内研修と意識改革: 全社的に情報開示の重要性を共有する研修を実施する。管理職や各事業部門にも投資家視点を浸透させ、必要な情報を適時IR部門に提供する姿勢を根付かせる。
経営トップが旗振り役となり、これらの体制・プロセス改革を推進することで、情報開示は企業文化の一部として定着します。開示の正確性・迅速性が向上すれば、市場からの信頼も高まり、有事の際の情報発信でもブレない対応が可能となります。また内部体制が整うことで、前述の各ポイント(株主対応、KPI開示、英文対応など)もスムーズに実行できるようになるでしょう。
編集後記
情報開示は単なる法令遵守の「守り」ではなく、企業価値向上のために活用する「攻め」の経営ツールへと変貌しつつあります。株主との建設的な対話を実現するには、必要な情報を適時適切に開示し、双方向のコミュニケーションを図ることが不可欠です。その過程で企業は自らを磨き、投資家からの信任を得て、成長資金を呼び込む好循環が生まれます。
情報開示の「守りから攻めへの転換」を本記事の内容をヒントに、自社の開示戦略を見直し、ステークホルダーとの対話を一段と深化させていかれることを期待しております。
参考情報(金融庁「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」議事録 等)