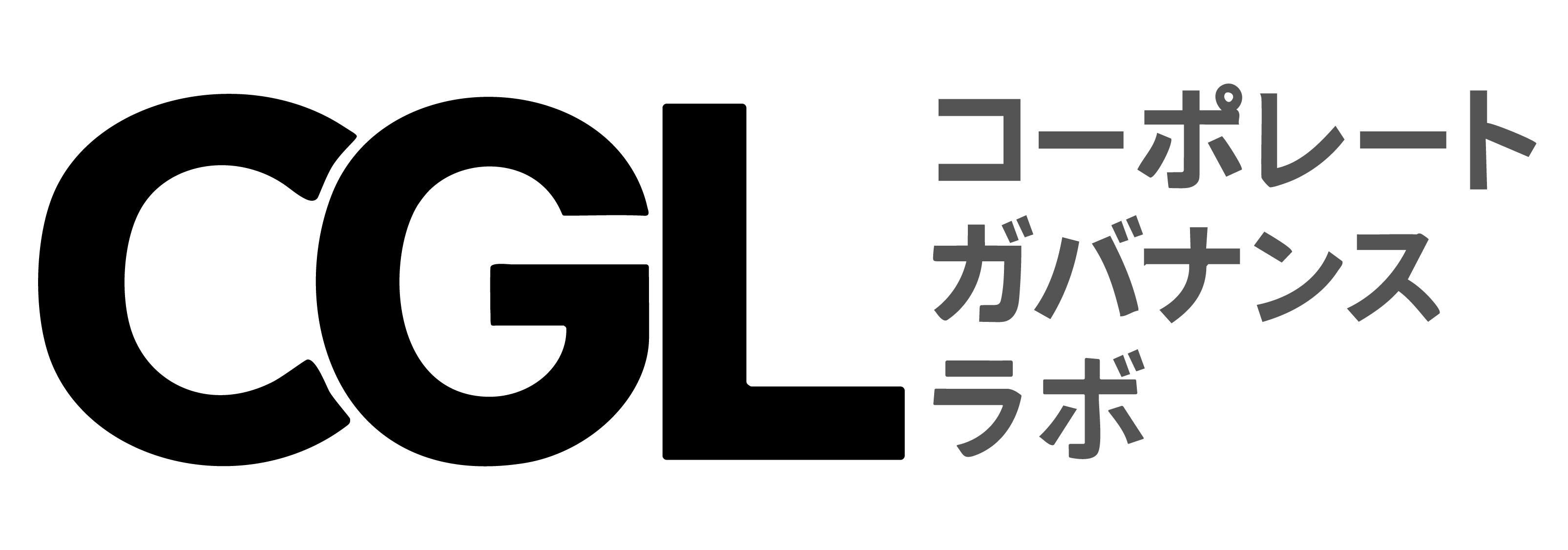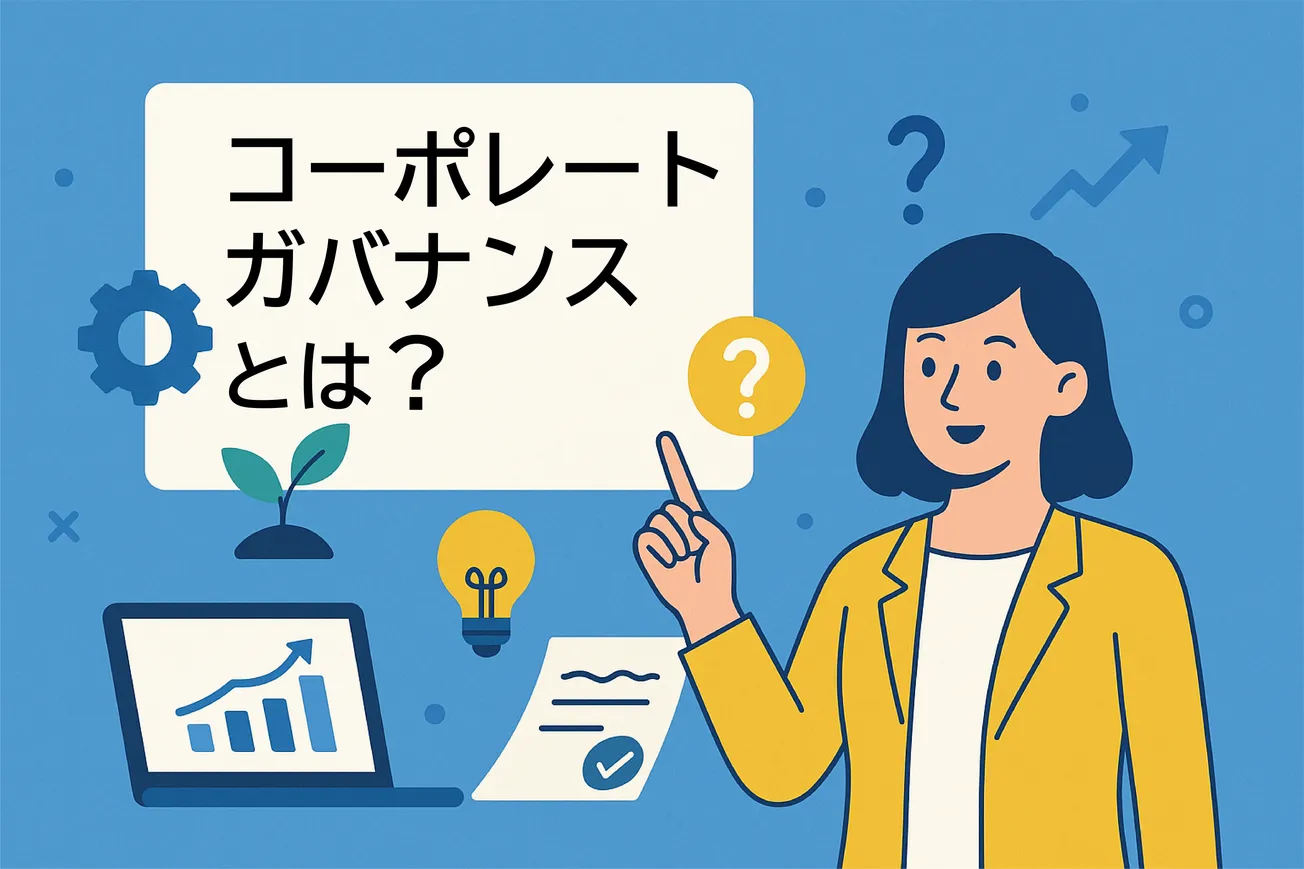目次
企業価値担保権付き融資で「前倒しの信用リスク評価」が進む
金融庁が公表した「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方(案)」は、単なる“担保”の拡充にとどまらず、将来を見据えたリスク評価の重要性を提起しています。これは米国で導入された CECL(Current Expected Credit Loss)モデルと本質的に通じる考え方であり、地方銀行にとっては融資審査・引当モデル・ガバナンスの全面的な見直しを迫る潮流です。事業性評価の強化を機に、地域企業の可能性を掘り起こすチャンスとして捉えることもできます。
なぜ今「企業価値担保権」なのか?
金融検査マニュアル廃止の影響
かつての金融検査マニュアルは、財務指標や担保・保証の有無による機械的な与信判断を誘発し、深い事業理解に基づく評価が形骸化した、という批判の声が上がっていました。
その結果、多くの地方銀行では**「業績が落ちればすぐ格下げ」**という、過去志向の運用が定着。結果的に将来性がある企業でも資金繰りが苦しくなると貸し渋りを受け、成長機会を逃すケースが指摘されました。
「事業性重視」への転換
こうした課題意識から金融庁はマニュアルを廃止し、借り手企業の将来キャッシュフローや事業価値を重視する「事業性評価融資」へかじを切っています。その施策の一つが、2024 年成立・2026 年施行予定の企業価値担保権。企業が保有する有形・無形資産を一括して担保化し、従来の不動産担保・保証と並ぶ新たな融資手法として位置づけられています。
企業価値担保権には「将来性の高い事業」をしっかりサポートする可能性がありますが、実際には売却価値の評価が難しいという悩ましさも。そこで金融庁は、引当上どのように考えるべきかを指針としてまとめたわけです。
CECL モデルとの“シンクロ”が示すもの
今回の金融庁ペーパーは、米国会計基準である**ASC 326(CECL)**を脚注で直接引用しながら、「定量だけでなく定性・将来要因を織り込んだ引当」を促しています。CECL では貸出を行った初日に、将来発生しうる損失を一括計上(取引をした「初日」に計上)するアプローチを採用。こうした「前倒しの損失認識」は、過去指標に依存していた従来モデルからの大きな転換を意味します。
「将来予想を不可避とする」両者の共通点
- 早期認識:企業価値担保権では「倒産リスクが低減されるなら初期引当を圧縮できる」と、いわば CECL 的発想を明示しています。
- 定量+定性要素の両立:CECL も金融庁ペーパーも、担保や保証を含むあらゆるリスク低減要素を正当に反映する一方、経営者の実力・業界展望など“数字に表れにくい情報”も見逃さない姿勢を強調しています。
- モデルガバナンス:日本でもモデル依存度が急速に増すなか、リスク管理や内部統制が不十分だと「恣意的な評価」や「過度な楽観」が生じかねません。両指針とも、モデル管理や検証体制の強化を繰り返し訴えています。
どこまで踏み込む? 日本版 ECL モデルへの布石
CECL は米国独自の基準ですが、国際会計基準(IFRS 9)も同様に**期待信用損失モデル(ECL)**を導入済みです。日本の会計基準(ASBJ)も同方向への改正が進められています。
つまり今回のペーパーは「企業価値担保権での具体的引当方法」にとどまらず、将来の日本全体の貸倒引当実務が CECL や IFRS 9 とほぼ同質になることを見据えた“橋渡し”的な意味をもつと言えます。
地方銀行にとって何が変わる? 具体的検討事項
それでは、今回のペーパーが地方銀行の融資実務に与える影響を整理しましょう。
「事業性評価」の精度が勝負を分ける
企業価値担保権付き融資は、いわば「企業の将来を担保に取る」という発想です。
- PD(倒産確率)の見極め:景気連動リスクや経営者交代リスクなどを予見できれば、無担保に比べてリスクが下がるはず。しかし、モニタリングを怠れば「事業が急速に悪化していた」ケースを見落とす可能性があります。
- 将来 CF を読む力:不動産担保に頼らない以上、「経営計画の実現性」や「市場成長性」を見極める金融知見が必須。事業性融資のノウハウが銀行の競争力に直結します。
引当モデル再構築の必要性
CECL や金融庁ペーパーのベースとなる「期待損失」は、過去データに加えて将来マクロ・業種見通し・経営者能力など定性要因も織り込む必要があります。
- 過去実績だけでは不十分:従来は財務指標中心で「資金繰り表が悪化したら要注意先」と機械的区分する手法が主流でした。今後はプロジェクション(予測)で倒産確率が下がると見なすなら、引当水準を引き下げられる反面、その評価根拠と精度が厳しく問われます。
- 複数モデル・シナリオ分析:将来予測には不確実性が伴うため、メインシナリオ+悲観シナリオといった形で複数パターンを比較し、最終判断に反映させる運用が望ましいです。これは CECL の米銀でも一般的な手法になっています。
ガバナンスと「モデルリスク管理」の強化
前倒し計上が可能だと、一時的には引当額を低減できるかもしれません。しかし将来が不透明な中で甘い見積をすれば、後々大きな毀損を被るリスクもあります。
- 独立した検証体制:モデル開発部署とバリデーション部署を分け、定期的に精度検証を行う枠組みが重要です。
- 取締役会レベルの監督:社内で開発されたモデルを経営陣がしっかり理解し、「甘くないか」「過度に保守的ではないか」を検証するプロセスが求められます。
- コンプライアンス+戦略の両輪:モデルリスク管理は単なるコンプライアンス対応でなく、戦略的な融資判断とも表裏一体。将来見通しを厳密にとらえる力が増せば、地域企業とのパートナーシップがより強固になり、新規事業などの成長機会を共創できる可能性も広がります。
未来を見据えた融資姿勢が地域を変える
企業価値担保権という新制度は、制度趣旨を踏まえて活用すれば 地域経済活性化のエンジンになり得ます。地方企業の中には、現行の不動産担保や信用保証協会で資金調達が進まないケースが多々あります。しかし、企業価値担保権の仕組みを通じて「将来収益」や「経営者の強み」をしっかり評価できれば、本来なら成長機会を開花できる企業を地域で支えられるかもしれません。
そのためには、単なる制度利用にとどまらず、CECL 的な視点で信用リスクを前倒しで捉え、定性情報まで織り込む評価体制がカギとなります。そこにこそ、地銀が新たな存在価値を発揮できるチャンスがあります。
今こそ“挑戦”が問われる
- 事業性評価を強化して新規案件の掘り起こしを目指す
- 貸倒引当モデルの整備を進め、金融庁ペーパーを踏まえたリスク管理態勢を構築
- 経営陣が「甘すぎる評価」「無意味に厳しすぎる評価」など両極端に陥らないようバランスを監督
- “事業性評価”の高度化は即時には完成しないが、モデルと実務経験の双方を積み重ねることで競争力を磨く
地方銀行は、地元企業と密着しているがゆえに日ごろから多彩な定性情報や経営者との対話機会を持っています。その強みをシステマチックに活かせるよう、「CECL/IFRS 9 的な前倒しの信用リスク管理」はもはや避けて通れない時代です。新担保制度を単なる法改正として捉えるか、未来指向の金融スタイルへと飛躍させる契機とするか─その選択が、今まさに試されているのではないでしょうか。
【編集後記】
本記事では「企業価値担保権付き融資」という一見専門的なトピックを、CECL との共通点という視点からひも解きました。実はこの両者が共有する“将来を見据えた損失見積もり”という発想は、表面的には地味に見えます。しかしその背景には、「日本の融資姿勢を本質的に変えたい」という意図が透けて見えます。
「担保・保証ありき」の判断から「事業価値の可能性をどう育てるか」これまでの当たり前を見直すのは、大きな勇気がいる作業です。しかしその先には、新たなビジネスチャンスや地域経済の再生という可能性が拓かれるかもしれません。