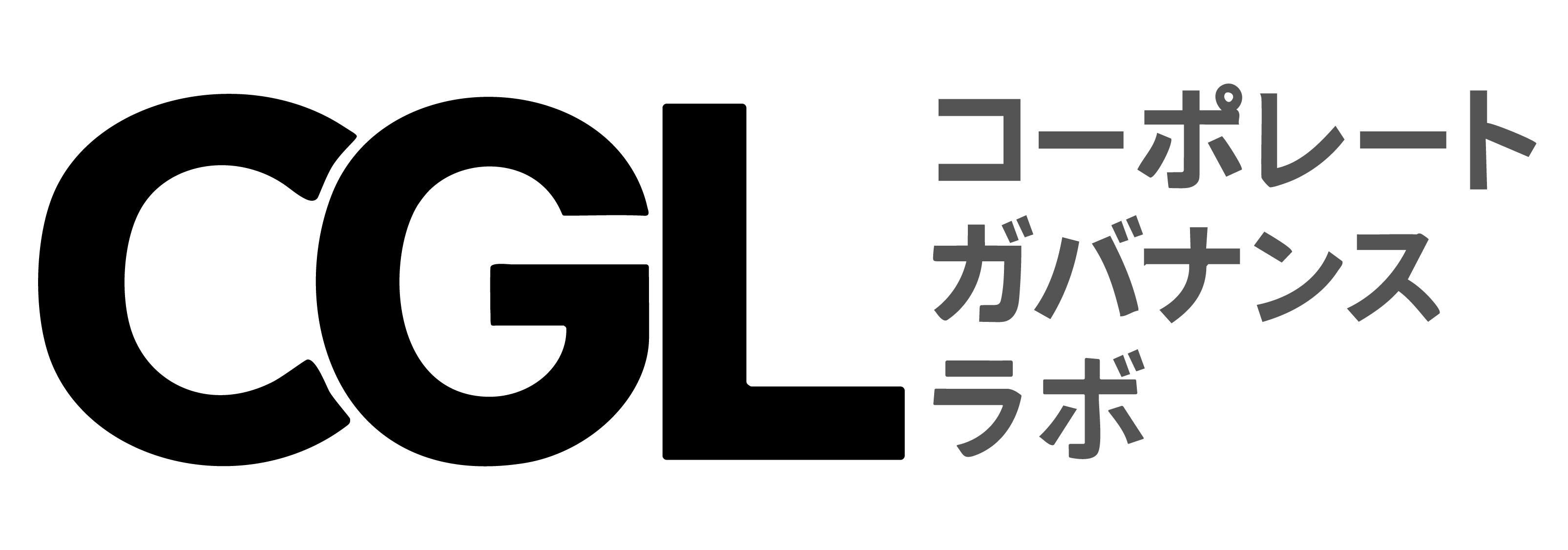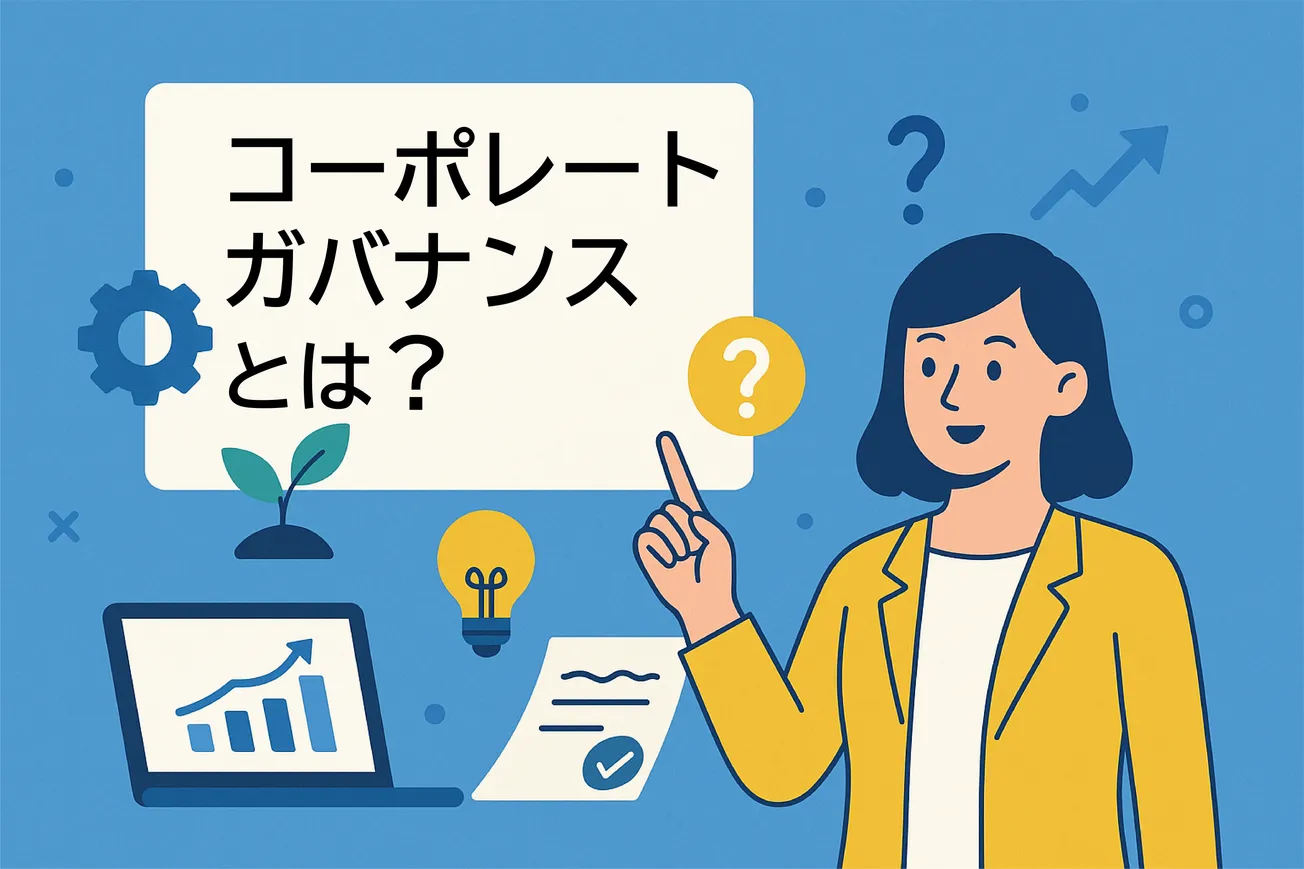目次
キーポイント
- 令和6年(2024年)6月に成立した「事業性融資の推進等に関する法律」は、不動産担保・個人保証に依存した従来の融資慣行を見直す目的で制定。
- 「企業価値担保権」を新設し、企業の無形資産や将来キャッシュフローを含む事業価値を包括的に担保に取れるようになる。
- 経営者個人保証の原則不要化により、事業承継や新規事業展開時の資金調達ハードルを下げる。
- 「認定事業性融資推進支援機関」が、融資を受ける企業と金融機関双方に助言を行い、事業計画の策定やモニタリングをサポート。
- 信託会社が担保権者(受託者)として、企業価値担保権を公正に管理・実行し、万一の際でも事業を大きく毀損しない形で回収手続きを進める。
はじめに
不動産担保や経営者の個人保証に過度に頼らない新たな融資制度が現実のものとなりつつあります。令和6年(2024年)6月、「事業性融資の推進等に関する法律」(以下、「事業性融資推進法」)が国会で成立・公布されました (事業性融資の推進等に関する法律 令和6年6月14日法律第52号 | 日本法令索引)。この法律は、不動産担保や個人保証に依存した従来の融資慣行を是正し、中小企業が事業に必要な資金を円滑に調達できる環境を整えることを目的としています (事業性融資の推進等に関する法律案 | 内閣法制局)。具体的には、企業価値担保権という新しい担保制度の創設などを通じて、金融機関が事業の将来性に着目した融資を行いやすくする枠組みを提供します。本稿では、この新法のポイントと実務上のメリット・留意点について、地方銀行の担当者の皆様向けに平易に解説します。なお、本法律は2024年6月に公布されていますが、施行日は公布から最長2年6か月以内(政令で定める日)とされており、今後順次制度整備が進められる予定です (「事業性融資の推進等に関する法律案」概要)。
事業性融資推進法とは何か?制度の概要と背景
「事業性融資の推進等に関する法律」は、中小企業やスタートアップ企業への融資の在り方を抜本的に見直すための新法です。2024年3月に政府から法案提出され、同年6月に可決・成立しました。背景には、金融機関の融資が不動産担保や経営者保証に偏重しがちで、無形資産しか持たないベンチャー企業や、個人保証がネックで思い切った事業承継・新展開に踏み出せない中小企業が十分な資金調達を得られないという課題がありました。この法律はそうした課題を解決するため、以下のような柱を定めています。
- 基本理念の明確化と国の責務: 事業の実態や将来性に着目した事業性融資を推進する基本理念を定め、国(政府)がその理念に則った施策を策定・実施する責務を負うことを明文化しました。金融庁内に関係省庁を集めた「事業性融資推進本部」(本部長:金融担当大臣)を設置し、事業性融資促進の基本方針策定など政策面の舵取りを行います 。これにより、政府一体となった支援体制の下で金融機関の事業性評価に基づく融資を後押ししていきます。
- 企業価値担保権の創設: 本法律の中核となる制度で、無形資産を含む事業全体の価値(企業価値)を担保に取る新しい担保権です(詳細は後述)。これにより、有形資産に乏しい企業でも事業計画や技術・ノウハウといった将来価値を評価した融資を受けやすくします。
- 認定事業性融資推進支援機関の創設: 事業性融資や企業価値評価に関する高度な専門知見を持ち、企業や金融機関に助言・指導を行う機関を政府が認定する制度も盛り込まれました。この支援機関が企業価値担保権の活用を実務面でサポートし、担保制度の周知・研究・普及にも努める役割を担います。
以上のように、事業性融資推進法はハード(制度設計)とソフト(支援体制)の両面から、「不動産担保・個人保証に依らない融資」の実現を目指しています。
企業価値担保権とは:無形資産も含めた新たな担保制度
本法律で創設された企業価値担保権とは、企業の総財産を包括的に担保とする新しい担保制度です。具体的には、事業者の現在および将来の財産を含む事業全体の価値を担保権の目的とします 。不動産や動産など特定の資産だけでなく、例えば技術・特許、ブランド力、顧客基盤、将来のキャッシュフローといった無形資産まで含めて担保に供する点が従来の担保制度と大きく異なります。これにより、十分な不動産を持たないスタートアップ企業等であっても、事業計画の将来性や保有する無形資産を評価材料として融資を受けられる可能性が広がります。
企業価値担保権を設定する契約(「企業価値担保権信託契約」と呼ばれます)は、債務者である事業者を委託者(信託財産を拠出する者)とし、専門の信託会社を受託者(信託財産を管理する受託者兼担保権者)とする信託の形で構成されます 。信託財産として事業者の総財産(将来取得するものを含む)を信託会社に預け、信託会社がその事業価値全体に対する担保権者となる仕組みです。このように信託の枠組みを使うことで、事業全体を一体として管理・処分できるようにし、万一の際も事業価値を損ねない形で担保権を実行できるようにしています。
なお、企業価値担保権付き融資を行う場合、金融機関は原則として経営者個人の保証を求めることができなくなります 。債務者による粉飾決算など特別な場合を除き、企業価値担保権を利用する際には経営者保証の徴求を制限する規定が設けられており、これによって「担保は事業の将来性、保証人は経営者個人」という従来型の融資慣行からの転換を図っています。つまり、この新担保を活用すれば経営者個人が私財を差し出すことなく資金調達しやすくなる点が大きなメリットです。
個人保証や不動産担保に依存しない融資慣行への転換
上記の企業価値担保権の導入によって、金融機関による融資姿勢にも変化が期待されています。法律の提案理由にもあるように、政府は「不動産担保や個人保証に依存した融資慣行の是正」を明確に掲げています 。企業価値担保権はその具体策であり、事業の実態や成長可能性に基づく評価(いわゆる事業性評価)を重視した融資を促すものです。
この枠組みの下では、金融機関は事業計画の内容や技術力、市場での優位性、知的財産などを総合評価して融資判断を行うことになります。担保として事業全体を押さえられる安心感があるため、従来は無担保扱いで敬遠されがちだった無形資産主体の企業にも資金供給しやすくなるでしょう。経営者保証についても先述のとおり原則不要となるため、経営者個人のリスクを抑えた融資が可能となり、事業承継時に後継者に過度なプレッシャーを与えない金融支援や、第二創業・新規事業展開に挑戦する経営者の後押しが期待されます。
もっとも、個人保証や不動産担保を外すことは金融機関側にとっても大きな転換です。事業性評価の高度化が求められるため、金融機関内部での「目利き力」強化や無形資産評価手法の確立が課題となります。そこで本法律では次のような支援策も用意されています。
認定事業性融資推進支援機関によるサポート
認定事業性融資推進支援機関制度は、新しい融資手法の円滑な普及・定着を図るために設けられた支援制度です。これは、事業性融資や企業財務に関する高度な専門知識を持つ法人などを、主務大臣(金融担当大臣等)※が公式に「事業性融資推進支援機関」として認定するものです。認定を受けた機関(以下、支援機関)は、融資を受ける企業や融資を行う金融機関と契約を結び、専門家の立場から双方に助言・指導を行う役割を担います。
具体的に支援機関が提供するサポート内容の例としては、以下のようなものが想定されています。
- 金融機関に対する支援: 無形資産評価や事業性評価の手法に関するアドバイス、融資実行後のモニタリング体制の整備支援、事業計画に基づく融資審査の高度化支援など。金融機関の「目利き力」向上を専門知見でバックアップします。
- 企業(借り手)に対する支援: 事業計画策定の助言、無形資産の価値を高めるための経営アドバイス、企業価値担保権の契約内容や効力・手続に関する丁寧な説明など。特に後者については法律上も支援機関の説明義務として規定されており、企業に対して企業価値担保権の仕組みや万一実行される場合の流れ等を事前によく説明することが求められます。
- その他の活動: 企業価値担保権の活用事例の収集・紹介、制度に関する調査研究や普及啓発セミナーの開催等 。支援機関は単に個別案件を支援するだけでなく、広く制度の定着に向けた啓蒙活動にも努めることとされています。
(※注) 「主務大臣」とは本制度を所管する大臣のことで、金融庁長官(内閣府特命担当大臣〔金融担当〕)のほか、中小企業政策を所管する経済産業大臣など関係閣僚が該当します。本法律では関係省令で具体的な所管を定める予定です。
支援機関制度により、金融機関は不足しがちな無形資産評価のノウハウを補完でき、企業側も専門家のサポートを受けながら安心して新しい担保制度を利用できるようになります。政府が認定した信頼性の高い支援者が間に入ることで、金融取引の円滑化・適正化が図られる点がポイントです。
信託会社が担う役割:担保権者としての機能
企業価値担保権制度のもう一つの重要なプレーヤーが信託会社です。本制度では、企業価値担保権の担保権者(担保の権利を保有・行使する者)は「企業価値担保権信託会社」に限ると定められました。企業価値担保権信託会社とは、本法律に基づき新設される信託業の免許を取得した信託会社のことで、企業価値担保権の設定を受ける専門の受託者です。言い換えれば、企業価値担保権による融資を実施する際には、銀行など貸し手金融機関が直接担保権を取るのではなく、必ずこの免許を持つ信託会社を介して担保設定を行うことになります。
では、なぜ信託会社を介在させるのでしょうか。その理由は、企業価値担保権という包括的な担保権を適切に運用し、かつ他の一般債権者との利益調整を図るためです。にあるように、事業全体を担保とするスキームでは、金融機関だけが強力な担保権を行使すると取引先(仕入先や顧客への債務)や従業員の給与債権など一般債権者が不当に害されるおそれがあります。そこで、中立的な信託会社が担保権者となり、法律で定められた手続に則って担保権を管理・実行する仕組みとしています。信託会社は受託者として企業の財産全体を信託財産として預かりながらも、企業の通常業務には支障が出ないよう管理を行い(企業は信託会社と信託契約を結んだ上で事業を継続します)、万一借入金の返済が不能となった場合に担保権の実行手続を主導します。
特に担保権実行時(=企業価値担保権の発動時)の役割が重要です。信託会社は担保権者として裁判所に対し担保権実行の申立てを行い、裁判所の下で事業の処理が進められます。具体的な流れとしては、裁判所が選任する管財人(破産管財人に類する立場の第三者)が会社の事業を引き継いで管理・運営しつつ、事業全体を第三者に譲渡する手続きを行います。この際、事業は解体されることなく一体として譲渡されるのが原則であり、譲渡に当たっては裁判所の許可が必要です。許可に際して裁判所は労働組合(従業員代表)や一般債権者にも意見を聞くなど、関係者の権利保護に配慮する仕組みとなっています。
譲渡代金の配分も法律でルールが定められています。まず事業継続に不可欠な費用として、従業員の未払給与や取引先への未払代金等(商取引債権・労働債権など)を優先弁済し、残りの代金から金融機関の貸付債権(担保権者である信託会社を通じて保護されている債権)への配当が行われます。このように、担保権の実行プロセスにおいても事業価値の毀損防止と一般債権者の保護が図られており、企業価値担保権は単なる貸し手有利の担保ではなく、事業継続性に配慮した新しいタイプのセキュリティだと言えます。
なお、企業価値担保権信託会社になるには金融庁(内閣総理大臣)の免許を取得する必要があります。信託業法上の新しい区分の免許が創設される予定であり、一定の資本金や体制整備など厳格な基準を満たした会社のみがこの免許を得られます。現在は制度開始に向けて詳細な基準策定が進められている段階です。一般的な信託銀行や信託会社が新たに免許を取得して担い手となることが想定されていますが、地域のプレイヤーでは例えば地方銀行系列の信託会社などがこの役割を果たす可能性もあります。
実務上の留意点:裁判所・行政機関の関与について
最後に、本制度の運用に関して地方銀行の担当者が押さえておきたい実務上の留意点として、関係機関(裁判所や行政当局)の関与状況を整理します。
- 裁判所の関与: 前述のとおり、企業価値担保権の実行(担保処分)は裁判所の監督下で行われます。通常の担保権実行(競売など)に比べると、裁判所を介した手続になる分だけ時間や手間がかかる可能性があります。もっとも、その分事業を清算せずに再生させる余地が確保され、従業員や取引先にも配慮した形で清算手続きが進むメリットがあります。金融機関にとっても、単純な担保回収ではなく事業譲渡による回収となるため、譲渡先への引継ぎや買い手探しといったプロセスに知見が必要になります。この点は支援機関や信託会社と連携しつつ進めることになるでしょう。
- 内閣総理大臣(金融庁)の関与: 企業価値担保権信託会社の免許付与や制度全体の監督は内閣総理大臣(実務上は金融庁)がおこないます 。したがって、本制度を利用した融資を行う際には免許を受けた信託会社との連携が不可欠です。現時点で銀行自身が直接この免許を取得して担保権者になることは想定されていないため、他社である信託会社(グループ内外を問わず)の協力を得る形となります。また、認定事業性融資推進支援機関の認定も主務大臣(金融庁・関係省庁)が行います。金融庁は本法律に基づき事業性融資推進本部を設置し基本方針を策定するなど制度運営の中心的役割を担います。地銀担当者としては、今後金融庁等から公表されるガイドラインや基本方針の内容にも注目し、自行の融資方針や審査体制に反映させていく必要があります。
- 金融機関・支援機関の実務対応: 本制度の活用に当たっては、金融機関と認定支援機関、信託会社の三者が連携する新たなスキームとなります。各者の役割分担(例えば、無形資産の評価は支援機関が助言、担保設定の契約実務は信託会社が担当、融資審査と実行は金融機関が担当 etc.)を明確にし、社内の関係部署とも協調してプロジェクトチーム的に進めることが想定されます。従来の不動産担保融資とは勝手が違うため、事前準備として契約スキームの研究や支援機関とのネットワーク作りが求められるでしょう。また、法律の施行時期が最長で2026年末頃まで猶予があることから、その間に実証事業やモデルケースの蓄積が期待されます。早い段階から情報収集しノウハウを蓄積することで、施行後にスムーズに制度を活用できるようになるでしょう。
まとめ
- 事業性融資推進法とは何か?制度の概要と背景
- 2024年に成立。不動産担保・個人保証に頼る慣行を改め、事業性評価に基づく融資を推進する法律。
- 企業価値担保権とは:無形資産も含めた新たな担保制度
- 企業の総財産(無形資産含む)を一体として担保化し、経営者個人の保証を原則不要化。
- 個人保証や不動産担保に依存しない融資慣行への転換
- 成長性や保有技術など、無形資産評価を重視し、創業・ベンチャー企業でも融資を受けやすく。
- 認定事業性融資推進支援機関によるサポート
- 企業・金融機関を支援する専門家を国が認定。事業計画づくりや無形資産評価を後押し。
- 信託会社が担う役割:担保権者としての機能
- 「企業価値担保権信託会社」が包括的担保権を管理。返済不能時も事業再生・継続の道を確保。
- 実務上の留意点:裁判所・行政機関の関与について
- 担保権実行は裁判所が監督し、信託会社・支援機関は金融庁の免許・認定を受け厳格に運営。
編集後記
企業価値担保権は、不動産担保や経営者保証だけでは測りきれない企業の本質的な強みを可視化し、活かすための大きな一歩だと感じます。コーポレートガバナンスの観点から見ても、事業性評価を重視した融資が普及すれば、経営者と金融機関の対話がより深まり、透明性の高い経営が根付いていくでしょう。企業が持つ“見えない価値”を、きちんと評価される社会が早く当たり前になってほしい――そんな期待を込めて、私たちも引き続き情報発信を続けてまいります。
<参考資料>関係省庁による公開資料やガイドライン等
- 金融庁「事業性融資の推進等に関する法律案 概要」2024年3月15日ほか
- 内閣法制局「事業性融資の推進等に関する法律案 提出理由」 (事業性融資の推進等に関する法律案 | 内閣法制局)
- 国立国会図書館「日本法令索引」同法の基本情報 (事業性融資の推進等に関する法律 令和6年6月14日法律第52号 | 日本法令索引)(法律番号、成立・公布年月日 等)
- 大和総研「事業性融資の推進等に関する法律案 概要」(平石研究員レポート) (「事業性融資の推進等に関する法律案」概要)